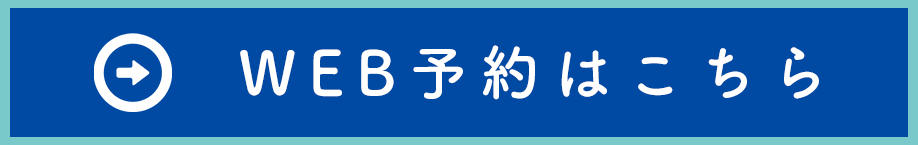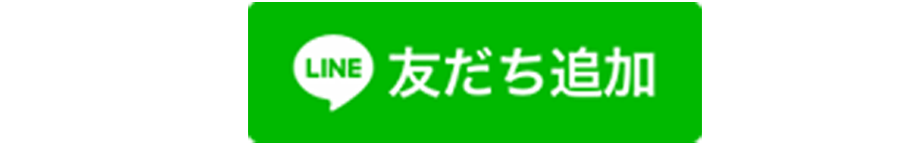症状から探す
胸やけ
胸やけとはみぞおちの上部あたりのやけるような感覚のことです。
胸やけ症状を有している患者様に合併しやすい症状として、呑酸(どんさん)という症状があります。
呑酸とは口の中に酸っぱいものが上がってくる感じやのどがヒリヒリしたり、やけるような感じのことです。

胸焼けの原因
日常生活においては、食道と胃のつなぎ目に存在する下部食道括約筋が主体となって胃酸が食道に逆流することを防いでいます。
一過性もしくは恒常的に下部食道括約筋の緩みが生じることにより胃酸逆流を引き起こしてしまいます。
これは、胸やけの原因疾患として一番頻度の高い逆流性食道炎の機序について述べたものです。
下記のように原因疾患がありえますので、付随する症状や症状が出現する機序も異なります。
よって治療法もことなりますので、疾患別解説をご参照ください。
胸焼けの原因疾患
- 逆流性食道炎(GERD)
- バレット食道
- 非びらん性胃食道逆流炎(NERD)
- 好酸球性食道炎
- 食道がん
- 胃がん
胸やけの検査
胃カメラ検査:原因疾患を検索し、治療方針の立案につなげてまいります。
胃もたれ
胃もたれとは、食事が消化されずに胃に残っているような膨満感、重苦しさなどの不快感の総称です。
日常的によく感じる症状なので経験したことがある方も多いと思います。
胃もたれの原因は様々であり、中には胃がんなどの重篤な疾患が隠れている場合もあるため、長期間症状が続く場合は注意が必要です。
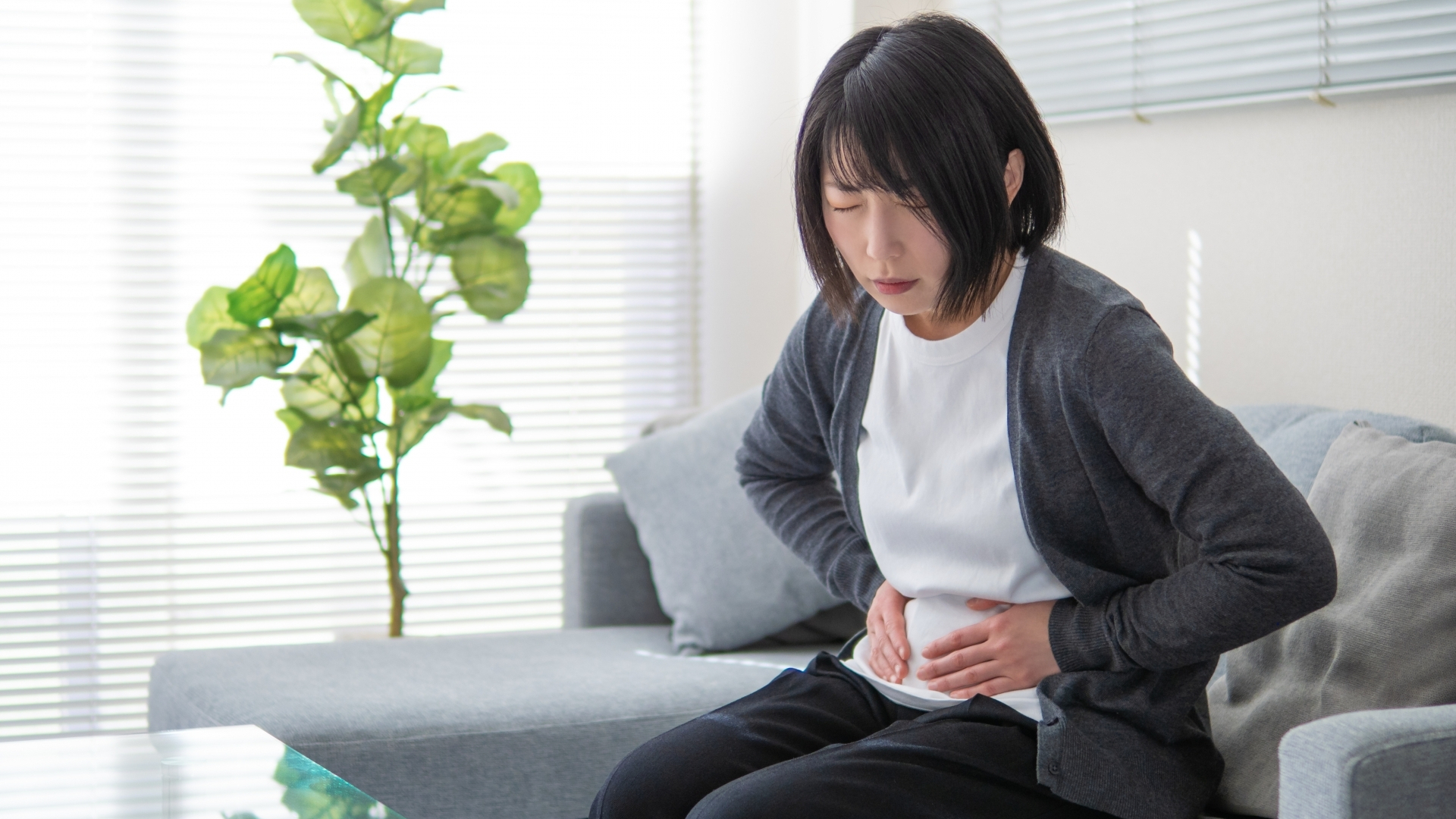
胃もたれの原因
- 暴飲暴食
脂っぽい食事の取りすぎは、胃腸の消化に負担をかけ胃もたれの原因になります。また、嗜好品(アルコールやタバコ、コーヒーなど)、塩分や香辛料の効いた食事(唐辛子や胡椒など)の取りすぎも胃粘膜の知覚過敏となり酸の分泌が強くなるため、胃もたれや胃の不快感を引き起こします。
- ストレス
日常的なストレスや不眠・過労で休息が十分とれていないと、自律神経のバランスが崩れて胃腸の動きが弱まり、早期満腹感や胃もたれ感を引き起こします。
- 加齢
年齢を重ねると、脂っぽい食事が若い時ほど摂れなくなる、少食になるなどの症状を感じる方が多くなります。これは加齢によって胃の蠕動運動が弱くなり、胃酸の分泌量が減るためです。
- 消化器疾患
食道がん、胃がん、逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、ヘリコバクター・ピロリ菌感染、胃・十二指腸潰瘍、胆のう疾患
一番気をつけなければいけないのが食道がんや胃がんです。胃もたれや嘔気などの症状がでてきてからでは進行してきている可能性もあります。
胃もたれが慢性的に持続する場合まずは、胃カメラや腹部超音波検査で消化管や周囲の臓器に異常がないか確認しましょう。
そして一番多くの方が診断されるのが、「機能性ディスペプシア」です。
胃カメラで何も所見がなく、他の原因疾患がないにもかかわらず、慢性的に胃もたれやみぞおちの痛みを訴える疾患を機能的ディスペプシアといいます。
こちらは、胃酸や胃の運動機能低下、ストレス、ヘリコバクター・ピロリ菌感染など多くの要因が関連しているといわれています。
胃もたれの治療
一時的な胃もたれでは、生活習慣の改善を行っていきます。
- 早食い、満腹を避け、よく噛んで腹八分を心がける
- 脂っこい食事を減らしバランスの良い食事を心がける
- アルコールなどの嗜好品や香辛料などの過剰摂取がある場合は、適量に控える
- 日常的なストレスや不眠、過労がある方は、ストレスを除外して十分な休息をとる
生活習慣の改善をしても効果が得られない場合は、消化器疾患が隠れている場合もあるので必ず胃カメラを行いましょう。
胃がん、食道がんなどの重篤な疾患が見つかった場合は、早期治療に努めます。
その他、胃・十二指腸潰瘍、逆流性食道炎などがあった場合は胃酸分泌を抑制する薬や、胃粘膜保護薬などの薬物療法が必要になります。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染が証明されたときは薬による除菌療法も併せて行っていきます。
胃に所見がなく機能性ディスペプシアが疑われる場合は、胃の出口の部分の蠕動運動を促進させる薬物療法を行います。
腹痛
腹痛は、腹部に生じる不快な感覚や痛み全般を指します。
腹痛の原因は様々で、冷えや食べ過ぎ、便秘など一時的なものもあれば、緊急手術が必要になるような重篤な疾患のこともあります。
また、腹痛は消化器疾患だけではなく、循環器疾患、婦人科疾患、泌尿器科疾患などの他の分野でも生じる症状のため、持続する場合は様々な検査が必要になることもあります。

腹痛の原因
腹痛の原因の多くは消化器疾患ですが、循環器疾患や婦人科疾患、泌尿器疾患などの多彩な分野の疾患の可能性があります。
ここでは注意すべき消化器疾患を紹介していきます。
- 胃・十二指腸潰瘍
ヘリコバクター・ピロリ菌感染や痛み止め(NSAIDs)の常用によって、胃や十二指腸の粘膜が攻撃され、潰瘍が生じます。
みぞおちの痛みの他、吐き気や胸やけを伴います。
潰瘍から出血すると貧血や黒色便が出現したり、潰瘍が深くなると穿孔することもあります。
- 急性虫垂炎
糞石や食物残渣などで虫垂が閉塞し、細菌感染することで起こります。
みぞおちの鈍い痛み(内臓痛)から始まり、右下腹部に限局した鋭い痛み(体性痛)へ変化していきます。
しばしば、発熱や食欲不振を伴います。
放っておくと虫垂に穴があいて腹膜炎になったり、膿瘍形成をきたす可能性もあり早めの受診が必要です。
- 感染性腸炎
ウイルスや細菌性などの病原菌が腸管に感染することで起こります。
腹痛の他に下痢、嘔吐、発熱などの症状がみられます。
冬に流行するノロウィルスやロタウィルスなどが有名で、多くは水分補給などの対症療法で軽快します。
しかし、中には抗生物質が必要になるような場合もあり症状が悪化する場合は注意が必要です。
- 大腸憩室炎
憩室とは大腸の壁が外側に突出し袋状になった部分です。
この憩室に、便や食物残渣が詰まって閉塞し、細菌感染をすることで憩室炎が起こります。
虫垂炎と同じ原理で起きますが、アルコール多飲や過労も関係しています。
上行結腸やS状結腸に起こりやすく、右下腹部やへそ下に疼痛を自覚することが多いです。
悪化すると、穿孔したり膿瘍を形成することもあり早めの受診が必要です。
- 虚血性大腸炎
便秘などで蠕動運動が亢進して血流の需要が高まったり、動脈硬化や脱水で血流が弱くなることで結果的に虚血を起こし、粘膜が脱落して起こります。
中年の女性に多く、突然の左側腹部~左下腹部痛が特徴です。
その後、徐々に血便が出現します。
多くの場合は、腸管安静のみで軽快しますが、悪化すると壊死を起こしたり点滴が必要になる場合もあります。
- 過敏性腸症候群
大腸カメラで異常がみられないにもかかわらず、便秘や下痢といった便通異常と腹痛が続く病気です。
腸の機能的な異常が原因とされ、ストレスや心理的異常と密接な関係があります。
便秘型と下痢型があります。
- 胆石発作
胆石が胆のうという袋状の臓器の頸部に嵌頓することで起こります。
右季肋部(右肋骨下)に激痛が起こり、右肩へ放散痛を伴います。
発熱や黄疸を伴うことがあります。
- 膵炎
アルコールや胆石が原因で膵臓の消化酵素が活性化し、自ら膵組織を破壊してしまう病気です。
上腹部(みぞおちから背中にかけて)に強い持続的な腹痛を生じます。
重症化すると命にかかわるため速やかな治療が必要となります。
腹痛の検査
腹痛は問診が非常に重要になります。
- 腹痛の出現した経緯
- 腹痛が急に来たのか徐々に来たのか
- 波がある痛みなのかずっと痛いのか
- 発熱や吐き気、下痢等の随伴症状はあるか
- 食事の内容や既往、内服薬の聴取
これらが診断材料になり、疑わしい疾患が絞れるようになります。
腹部の触診を行い、腹痛の部位や腹膜刺激症状があるかどうか、腫瘤があるかなどを調べます。
- 血液検査
- 心電図
- 上部内視鏡検査
- 下部内視鏡検査
- 腹部超音波検査
- CT検査
- MRI検査
- 細菌培養検査
上記の検査を行い、確定診断をつけていきます。
診断に基づいて、内服や点滴といった保存的加療や手術での外科的治療を行っていきます。
便秘
便秘症とは、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」をいいます。
要は、「便がでない、便が硬い、お腹が苦しい、スッキリ出にくい、残便感がある」といった不快感全般のことです。
便が腸に長く停滞することで、水分が吸収され硬い便になります。

便秘の原因
便秘の原因は様々です。
腸が物理的に細くなって出なくなる原因もあれば、腸の蠕動運動が低下して便を押し出せなくなる原因もあります。
- 消化器系の疾患
大腸がん、腹腔内腫瘍、クローン病、虚血性腸炎、巨大結腸症、直腸瘤など
- 消化器系以外の疾患
糖尿病、甲状腺機能低下症などの内分泌疾患や神経筋疾患、膠原病など
- その他
ストレスや環境の変化などの心因性、特定の薬剤、食物繊維や水分不足など
一番心配なのは、ただの便秘だと思って放置することです。
悪性疾患が隠れている場合があるので便秘が続く場合は必ず大腸内視鏡検査を行って腸内を確認しましょう。
下痢
下痢とは、何らかの原因によって便中の水分量が増え、軟便や水様便となった状態を指します。
下痢は一時的なものから、慢性的なものまであり、様々な原因があります。
急性下痢
約1~2週間持続する。腹痛、ときに発熱を伴うことがあります。
ウイルスや細菌による感染性腸炎、薬剤性、虚血性腸炎などの原因が挙げられます。
症状は数日から1週間程度で自然に治まることが多いです。
しかし、抗生物質が必要になったり、重症化する可能性もあるため注意が必要です。
慢性下痢
2週間以上続く下痢を指します。
クローン病や潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、大腸がんなどの消化器系の疾患の他、バセドウ病や副腎皮質機能低下症、ホルモン産生腫瘍、糖尿病、アミロイドーシスなどの内分泌疾患やストレス、食生活の乱れなどが原因となることが多いです。
慢性的な下痢は、重篤な疾患が隠れていることもあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
注意が必要な症状
- 高熱や激しい腹痛
- 血便や粘液を伴う便
- 長期間にわたる下痢(1週間以上)
- 脱水症状(のどの渇き、尿の回数の減少、尿が濃い)
- 体重の減少
上記のような症状があらわれた場合は、速やかに医療機関にご相談ください。
下痢のときの食事の注意点
下痢症状があるときは、極力食事は控えて腸管安静に努めましょう。
その代わり、脱水を防ぐために必ず水やお茶、経口補水液、スポーツドリンクなどの水分をこまめに取りましょう。
食事が取れるときは、おかゆやゼリーなどの消化によい食事をおすすめします。
辛いものや油分の多いもの、アルコールなどの刺激物は避けるようにしましょう。
下痢の治療
下痢はアルカリ性の水分が大量に奪われるため、水分補給が重要です。
多くの場合は水分補給で自然軽快しますが、感染性腸炎では細菌によっては抗生物質が必要になる場合もあります。
薬剤や特定の食品による下痢の場合は、原因薬剤・食品を速やかに中止し腸管安静を保つことで治療します。
ストレスや心的要因がある場合は、ストレスの原因を除外し、休養しましょう。
下痢が長期に持続する場合は、クローン病や潰瘍性大腸炎、大腸がんなどの消化器疾患が隠れている場合もあり、大腸内視鏡検査での精査を必ずしましょう。
血便
血便とは、血液が便とともに肛門から排泄されることです。
排便後にティッシュに血が付いた、便器の中が赤くなったということがあれば血便の可能性があります。
これは、消化管のどこかで出血が起きていることを示しています。
血便の色調や状態によって、出血の原因や出血部位のヒントが得られることもあります。
血便の原因
- 消化器系の疾患による原因
食道・胃静脈瘤破裂、胃・十二指腸潰瘍、急性胃粘膜病変、食道がん、胃がんなどの上部消化管の疾患は黒色便をきたします。
虚血性腸炎や大腸憩室出血、薬剤性腸炎、痔核・裂肛、潰瘍性大腸炎、クローン病、感染性腸炎(アメーバ赤痢、腸管出血性大腸菌など)、大腸がんなどの下部消化管の疾患は血便をきたします。特に、大腸がんや胃がんなどの悪性腫瘍も血便の原因となることがあり、内視鏡検査による早期発見・早期治療が重要です。
- 消化器系以外の疾患による原因
消化器系以外の疾患でも血便が起こる場合があります。
特定の薬物によって起こる薬剤性腸炎、膠原病による腸炎、肝胆膵疾患(膵がんや胆道がん)、血液疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、DIC)、外傷や手術後の合併症などが考えられます。