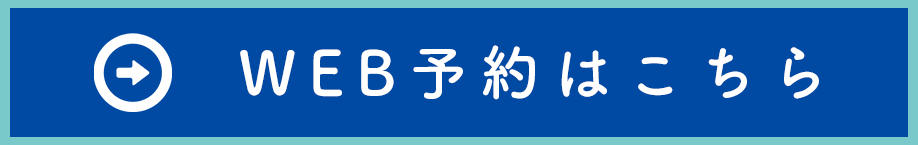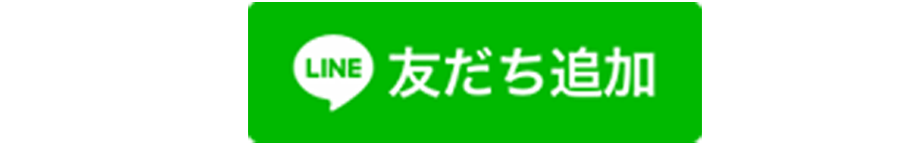病名から探す
大腸がん
大腸は回盲部~肛門までの1.5m程度の管腔臓器で、消化されてきた食物残渣から水分を吸収し、便を作ります。
大腸は結腸と直腸からなり、さらに結腸は上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸に分けられます。
大腸がんは、この大腸の粘膜に発生する悪性の腫瘍です。
大腸のポリープががん化する場合と正常な粘膜に直接がんが発生する場合があります。
大腸がんは、食事の欧米化や高齢化に伴い日本で罹患率、死亡率ともに増加傾向にあります。
早期発見、早期治療が非常に重要となるため、定期的な内視鏡検査が推奨されています。

大腸がんの症状
早期の大腸がんではほとんど症状はでません。
進行すると下記の症状がでることがあります。
【よくある症状】
- 血便・粘血便
- 便通異常(便秘、下痢、便が細くなる、便が残る感じ)
- 貧血
- 腹痛
- 腸閉塞、嘔吐
- 原因不明の体重減少
下行結腸やS状結腸、直腸のがんでは硬い便が通るため、便が細くなったり、便が詰まって腸閉塞症状(腹痛、嘔吐)を起こすことが多いです。一方で、まだ泥状の便が通る盲腸や上行結腸、横行結腸ではがんが出来ても症状が出にくく、腹部のしこりや貧血で発見される場合があります。いずれにしても、症状が出た時には進行している可能性が高いので定期的な内視鏡検査が非常に大切です。
大腸がんの検査
大腸がんの検査方法として、主に以下の方法があります。
- 便潜血反応検査
自覚症状のない大腸がんを発見するため、本邦では40歳以上を対象に市町村単位で便潜血検査による検診が行われています。
肉眼的には確認できないような微量の血液を検出する検査です。
2日間に分けて便を採取し検査しますが、1日でも陽性が出た場合は内視鏡検査での精査をおすすめします。
しかし、早期のがんでは必ずしも便潜血検査が有効なわけではなく、定期的な大腸内視鏡検査が大切になります。
- 大腸内視鏡検査
下剤で前処置を行った後、肛門から内視鏡を挿入し、直接全大腸の粘膜を観察する検査です。
病変が見つかった場合、その場で詳細な観察を行い、質的診断やがんの深さを予測することができます。
必要があれば、その場で生検や切除を行います。
当院では苦痛のほとんどない検査を行っています。
内視鏡専門医が丁寧な観察、治療を行いますので定期的な検査をぜひご検討ください。
- 注腸検査、3DCT
下剤で前処置を行った後、肛門から造影剤と空気を注入し、レントゲンを撮る検査が注腸検査です。
造影剤は入れずに空気をいれCT検査を行うのが3DCT検査です。
どちらも間接的に病変の画像を描出し検出する検査になります。
客観的に病変の位置を描出できるのはメリットですが、病変があった場合に直接観察ができず、後日内視鏡検査での精査を行う必要があり、2度手間なのがデメリットになります。また、平坦な病変や陥凹した病変を見つけにくいのもデメリットとしてあります。当院では、直接粘膜を観察し、治療できる内視鏡検査をおすすめしています。
大腸がんの治療
大腸がんの治療は、内視鏡治療、手術療法、化学療法があります。進行の程度によって治療法を選択しますが、原則として切除できるものは全て切除していきます。切除不能の場合や進行がん切除後に転移した場合、化学療法を選択していきます。
内視鏡治療は粘膜内または粘膜下層に軽度浸潤したがんについて、内視鏡からナイフやスネアなどの器具をだして病変を切除する治療法です。通常の内視鏡検査と同様の検査となりますので体の負担が少ないというメリットがあります。切除した検体は病理検査に提出し、がんの深さなどの病理的評価を行います。基準を満たしていない場合、追加で腸を切除することもあります。
内視鏡的に切除できない場合、手術療法が選択されます。
がんを含む腸管の切除と支配血管、周囲のリンパ節の郭清を行います。近年は腹腔鏡手術が主流で、傷が小さく、術後の痛みが少なく、回復が早いというメリットがあります。しかし、高度な進行がんや腸閉塞などの併存疾患がある場合は開腹手術が適しており、腹腔鏡では困難な場合もあります。
いわゆる抗がん剤で腫瘍の縮小や再発の抑制、予後の改善を目的に使用します。手術前に行う術前化学療法、手術後に行う術後化学療法、切除不能な進行・再発症例に行う全身化学療法に分けられます。複数の薬剤を使用しますが、薬が体に合わなかったり、効果がなくなれば違う薬剤に変更して治療をすすめていきます。
大腸がんの予防
- 生活習慣を改善する
高脂肪食や牛肉・豚肉などの赤肉類の過剰摂取は大腸がんのリスクを高めると考えられています。
一方、食物繊維や野菜・果物の多摂取は大腸がんのリスクを下げると考えられています。
食物繊維は腸内の嫌気性菌の繁殖を抑制し、便のカサを増やすことで便中の発がん物質を希釈し、暴露時間を減らすためと考えられています。また、運動不足は大腸がんの中の結腸がんのリスクを増大させるため、定期的に適度な運動をしましょう。
- 喫煙・飲酒を控える
喫煙は食道がん、胃がん、大腸がん、肝細胞がんなど多くのがんのリスクになることが示されています。
喫煙は何らかのがんになるリスクが約1.5倍も高まることがわかっています。
また、飲酒も大腸がんのリスクを上げると報告されています。
- 検診を定期的に受ける
上記の予防を行っても大腸がんのリスクを下げられますがゼロにすることは難しいです。
しかし、大腸がんになっても早期に発見して治療すれば100%治すことができます。
そのために大切なのは定期的に大腸がん検診を受けることになります。
40歳以上になれば便潜血反応での検診はもちろん、大腸内視鏡検査で大腸粘膜に病変がないか確認することをお勧めします。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる大腸の炎症性腸疾患です。
この炎症は主に大腸の直腸から始まり、連続的、そして上行性に広がっていく特徴があります。
炎症の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的な要因や免疫系の異常、食生活などの環境要因などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。
最近では腸内フローラの研究が進み、潰瘍性大腸炎では腸内細菌の種類や量が健常人とは異なると報告されています。
子供から高齢者までの全年齢層で発症し、20~35歳くらいに発症のピークがあります。男女差はありません。
このように原因不明の慢性の疾患のため、日本では「指定難病」に定められ医療費助成の対象となっています。
H25年度末時点で患者数は約16万6060人で人口10万人当たり約100人程度の割合で発症します。
潰瘍性大腸炎は病変の広がりや状態によって下記のように分類されます。
①病変の広がりにより直腸のみの「直腸炎型」、直腸~下行結腸までの「左側大腸炎型」、横行結腸より口側に広がる「全大腸炎型」に分類されます。
②病期により「活動期(症状が悪い時期)」と「寛解期(症状がおちついている時期)」に分類されます。
③重症度により「軽症」「中等症」「重症」「劇症」に分類されます。
④臨床経過により「再燃寛解型」「慢性持続型」「急性劇症型」「初回発作型」に分類されます。
潰瘍性大腸炎の症状
特徴的な症状として以下の3つがあります。
- 下痢
- 粘血便
- 腹痛(便がでないのに頻回に便意を催すしぶり腹をきたす)
重症になると下痢回数は増え、血性下痢、持続した腹痛をきたします。さらに以下のような全身症状が起こります。
- 発熱
- 貧血、頻脈
- 体重減少
その他にも腸管内の癌や中毒性巨大結腸症、感染症の合併や、皮膚・関節・目等の腸管外に合併症を生じることもあります。

潰瘍性大腸炎の検査方法
1日の排便回数や便の性状(軟便、泥状便、水様便)、粘血便・腹痛の有無等の症状の問診や腹部診察に加えて下記のような検査を行います。
- 血液検査
血液検査では炎症の程度(白血球数、血沈、CRP)、貧血(Hb)、栄養状態(TP、Alb)、薬剤の副作用の有無などのチェックを行い、体の状態の把握や重症度の判定のため定期的に実施します。
- 便検査
炎症によるわずかな出血があるかを確認する便潜血検査、細菌の感染が疑われる場合の便培養検査などを行うことがあります。
最近では腸管粘膜の炎症を評価するため便中カルプロテクチンの測定が用いられています。
- 大腸内視鏡検査
潰瘍性大腸炎の確定診断を行うために必要な検査です。
大腸の粘膜を直接観察し、炎症の範囲や程度を観察します。
生検で組織を病理検査に提出し、似ている病気との鑑別を行います。
また、確定診断がついた後も、症状が悪化して新たな治療法を検討する場合や、逆に症状がおちついて治療を緩和する場合に大腸内視鏡検査が行われます。
また、長期経過例では大腸がんの発生リスクが高まるため、無症状でも定期的な大腸内視鏡検査が推奨されます。
潰瘍性大腸炎の治療
潰瘍性大腸炎の治療では「寛解期」の維持を目指します。
炎症が落ち着いている状態をできるだけ長く保つことで、手術の回避や合併症や大腸がんのリスクを軽減することができます。
- 5-アミノサリチル酸薬(5-ASA)製薬
軽症~中等症に有効。炎症を抑えることで腹痛、下痢、血便の症状を改善する。
再発予防にも効果がある。
- 副腎皮質ステロイド薬
中等症~重症に使用される。炎症を抑える効果は高いが再燃防止効果はない。
- 血球成分除去療法
ステロイド薬が無効な活動期に使用される。
- 免疫調整または抑制薬
ステロイド薬を中止すると悪化する場合やステロイド薬が無効な場合に使用される。
- 抗TNFα受容体拮抗薬
有効性が高く、安定した状態を維持することができる点滴または皮下注射薬。
潰瘍性大腸炎の治療では「寛解期」の維持を目指します。炎症が落ち着いている状態をできるだけ長く保つことで、手術の回避や合併症や大腸がんのリスクを軽減することができます。
内科的治療が無効な場合(特に重症例)、出血や穿孔例、大腸がんがある場合に選択され大腸全摘を行います。
クローン病
クローン病は、口から肛門までの全ての消化管にびらんや潰瘍などの炎症を起こす可能性がある慢性の炎症性腸疾患です。
病変の部位は小腸か大腸が多く、小腸末端に好発します。非連続性で正常な粘膜が間に介在するのが特徴です。
また、病変は粘膜だけにとどまらず、消化管の壁全層に発生し、腸の内側が狭くなる「狭窄」や他の臓器や体の外側に通り道を作る「瘻孔」を起こすことがあります。
この疾患は遺伝的な要因や環境、免疫系の異常、ウィルスや細菌感染の影響など複数の要因が関与していると考えられています。
10代~20代の若者に好発し、男女比は2:1と男性に多いです。
根治治療がなく、長期治療が必要なため、日本では医療費助成の対象となる「指定難病」になっており、2018年時点で患者数は約4万2548人で人口10万人当たり約33人程度の割合となります。
クローン病は病変部位によって下記のように分類されます。
①小腸型:病変が小腸に限られる
②大腸型:病変が大腸に限られる
③小腸大腸型:小腸と大腸に病変があり、この型が最も多い
④特殊型:上記に当てはまらない部位に病変がある
クローン病の症状
- 下痢
- 腹痛
クローン病では半数以上の患者さんに腹痛と下痢がみられます。
- 発熱
- 下血
- 貧血
- 腹部腫瘤
- 全身倦怠感
- 体重減少
クローン病に特徴的な症状として肛門病変があります。消化管の慢性的な炎症によって、肛門部に瘻孔をつくる「痔瘻」や肛門周囲に膿の袋を作る「肛門周囲膿瘍」があります。また、腸管外の合併症として関節炎や虹彩炎、皮膚症状などがみられます。
症状が落ち着いている「寛解」と症状が悪化している「再燃」を繰り返すことが特徴であり、寛解期でも炎症が続くため「がんを合併」することもあります。
クローン病の検査
1日の排便回数や便の性状(軟便、泥状便、水様便)、肛門病変の有無等の症状の問診や腹部診察に加えて下記のような検査を行います。
- 血液検査
血液検査では炎症の程度(白血球数、血沈、CRP)、貧血(Hb)、栄養状態(TP、Alb)、薬剤の副作用の有無などのチェックを行い、体の状態の把握のため定期的に実施します。
- 内視鏡検査
内視鏡検査は、診断確定のために必須の検査です。口腔~肛門まで病変ができる可能性のある病気なので上部内視鏡検査、小腸内視鏡検査、大腸内視鏡検査などが行われます。最近では狭窄のない症例については、小腸カプセル内視鏡の選択肢もあります。下剤で前処置した後に小型カメラ搭載のカプセルを飲み込み口から肛門まで連続撮影を行います。
これらの内視鏡検査では、直接内部を観察するため、クローン病に特徴的な所見の有無や炎症の部位や程度、狭窄(狭くなること)や肛門病変の有無など、詳細な情報を得ることができます。粘膜を生検し、病理学的検査に提出することでクローン病に特徴的な所見が得られることもあります。
- 腹部CT、MRI、超音波検査
これらの検査は直接器具を体内に挿入する必要がないため患者さんの負担が少ないです。
消化管以外の臓器や組織の状態を確認でき、クローン病特有の消化管外の膿瘍や瘻孔などの評価に用いられます。
MRIは肛門部病変・瘻孔に対して優れた検査です。
クローン病の治療
- 5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤
軽症から中等症の患者さんに用いられる基本の薬で、大腸の炎症を直接抑える効果があります。
寛解の導入だけではなく寛解の維持にも使用されます。
- 副腎皮質ステロイド薬
中等症から重症の患者さんに用いられ、5-ASA製剤の効果が不十分だった場合や炎症が強い時に使用します。
再燃防止効果はありません。
- 免疫調節薬
主に中等症以上の患者さんに用いられ、寛解導入目的や、ステロイド依存の患者さんのステロイド減量・中止と寛解維持を目的に使用されます。
- 生物学的製剤
化学合成された薬ではなく生体が作るたんぱく質を薬剤として利用している薬です。
従来の治療で炎症が抑えられない場合に用いられる強力な薬です。寛解の導入や寛解の維持に用いられます。
- 栄養療法
腸に炎症が起き、腸の機能が低下すると、栄養が吸収できず全身状態の悪化につながる可能性があります。
脂肪を制限した栄養剤を摂取することで、腸管の負担や刺激を軽減し、炎症をコントロールする目的があります。
クローン病は、薬物療法などの内科的治療で炎症をコントロールするのが原則ですが、主に以下のような場合には手術が考慮されます。
- 内科的治療の効果が乏しい場合
- 難治性の狭窄(腸管の内腔が狭くなること)
- 腸閉塞(腸が狭くなり口側に腸液や食物残渣が停滞すること)
- 穿孔(腸に穴があくこと)
- 瘻孔(腸管の外に臓器や体外との通り道ができること)
- 大量出血
- がんの合併
- 肛門周囲膿瘍や排膿の多い有痛性の痔瘻など
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群(Irritable bowel syndrome:IBS)とは、腸管に器質的病変がないにも関わらず、便秘や下痢といった便通異常や腹痛が続く大腸の機能性疾患です。日本ではIBSの患者さんはおよそ10人に1人いるとされています。
20~40代に好発し、加齢とともに有病率が低下する傾向があります。
便通異常のタイプから4つに分類されます。
- 便秘型:硬便・兎糞状の便が出ることが多い
- 下痢型:軟便・水様便が出ることが多い
- 混合型:便秘と下痢を繰り返す
- 分類不能型:前述の3つにあてはまらないタイプ

過敏性腸症候群の原因
IBSの原因は明らかとなっていませんが、腸内細菌や神経伝達物質、内分泌物質、遺伝などの複数の要因によって消化管運動の異常や消化管の知覚過敏をきたすと考えられています。IBSの病態にはストレスが深く関与しており、消化管刺激に対する中枢反応の増強が確認されています。また、最近では細菌やウィルスによる感染性腸炎からの治癒後にIBSの発症率が増加することが報告されています。感染性腸炎の約10%にIBSを発症し、リスク因子としては女性、若年、心理的問題があると報告されています。また、高カロリー食・高脂肪食などにより消化に負担がかかり、IBSの引き金になることがあります。
過敏性腸症候群でみられる症状
IBSの症状は命にかかわる事はほとんどありませんが、日常生活に支障をきたす可能性は大いにあります。
精神的な不安や緊張などが関係していることが多いため、食後や電車内で突然便意をきたしてしまう不安があり、その不安から症状がさらに悪化して外出できなくなることもあります。
また、仕事の日だけ症状がでる不安があって仕事に行けなくなることもあります。
日常生活に支障をきたしている場合は、速やかに医療機関に相談しましょう。
- 排便に伴う腹痛と排便で緩和する腹痛
- 排便の頻度や便の硬さの変化によって変化する腹痛
- ガスがよく出る、お腹が鳴る、お腹が張る感じ
- 便に粘液がまじる
- 排便後の残便感
過敏性腸症候群の診断
IBSの診断は身体診察では何の異常もないため、主に問診で行われます。積極的にRomeⅣ診断基準(2016年改訂)を使用して行います。
【RomeⅣ診断】
腹痛が過去3か月間に少なくとも週1回の頻度で生じ、かつ下記の2つ以上の項目を満たす場合に診断されます。
- 排便に関連する痛みがある
- 痛みが排便頻度の変化に関連している
- 痛みが便の硬さの変化に関連している
他の原因疾患がないことが診断の上で重要になるため必要に応じて以下の検査が行われます。
- 一般臨床検査(血液検査・尿検査・便潜血検査)
- 大腸内視鏡検査
- 腹部CT検査
過敏性腸症候群の治療
主な治療は生活習慣についての指導やアドバイス、薬物療法になります。
まずは、十分な睡眠、規則正しい生活や食事(低FODMAP食)、運動を勧めます。
これで改善しない場合には、セロトニン拮抗薬(イリボー®)、漢方薬などの薬物療法を行います。
抑うつ気分などがあるときは、抗うつ薬や向精神薬などを用いることもあります。
当院は過敏性腸症候群の治療の経験が豊富で、患者さまの症状に合った適切な治療法を提供します。
虚血性腸炎
虚血性腸炎は、大腸の血流が一時的に減少することで大腸に炎症が生じ、腹痛や血便が起こる疾患です。
この疾患は、日常の診療でよく遭遇し、便秘をきっかけに発症しているケースが多いです。
血流が悪くなる疾患なので、動脈硬化がある高齢者や循環器系の疾患を持つ人に多く見られます。
軽症なことがほとんどで予後は良好ですが、中には大腸が壊死する場合もあり注意が必要です。
虚血性腸炎の原因と症状
大腸に血液を送る役割を担う動脈の血流が阻害され、大腸への血流が一時的に減少することにより大腸の粘膜に損傷がおき、潰瘍や出血を引き起こします。血管側の原因と腸管側の原因がそれぞれ複雑に絡んで発症すると考えられています。
- 血管側の原因
高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病や動脈硬化を起こしやすい基礎疾患のある方
- 腸管側の原因
主に便秘。便秘による硬便を押し出そうといきむことや、蠕動運動が活発になることで相対的に大腸粘膜への血流が低下します。
通常は排便後などに突然にシクシクとした腹痛があり、粘膜傷害が悪化すると下痢や血便が出現します。
下行結腸やS状結腸に好発するため左下腹部痛が多いのが特徴です。
虚血性腸炎の検査
- 血液検査
発症初期に白血球増加やCRP上昇、赤沈亢進などが見られます。壊疽型ではCKや乳酸の上昇、代謝性アシドーシスなどを認めますが、一般に遅れて上昇してきます。
- 内視鏡検査
内視鏡検査は、虚血性腸炎の診断に非常に有効な方法です。大腸の粘膜を直接観察し、縦走する発赤やびらん・潰瘍、出血、浮腫を観察することができます。組織を採取することで確定診断を付けることもできます。ただし、症状が出現した急性期では、腸管が脆弱になっている可能性があり危険なため、落ち着いてからの検査がお勧めです。
- 腹部CT検査
虚血部分と一致して連続した壁肥厚像が見られます。造影CTでは3層構造が見られ、特に粘膜下層に高度の浮腫性肥厚が見られます。腹腔内遊離ガスや門脈内ガス、腸管壁内ガスがみられた場合は壊疽型を疑う必要があり、非侵襲的で客観的な診断をすることができます。
虚血性腸炎の治療
腸の負担を減少させるため、一時的に食事を中止します。飲水はしていただいて構いませんが、重症度によっては絶飲食にし、点滴を行う場合もあります。炎症を抑えるための抗生物質投与を行うことがあります。
壊疽型で腸管の全層壊死や血管手術の合併で虚血性腸炎が生じた場合は手術が選択される場合があります。
大腸憩室炎
大腸憩室炎は、大腸の壁に小さな袋状の突出部(憩室)が形成され、その憩室が炎症を起こす病気です。
この憩室は、大腸の筋層の脆弱部分から粘膜と粘膜筋板が脱出することで形成されます。
日本では右側結腸に多いとされていますが、高齢化や欧米化の食事に伴い近年は左側結腸(S状結腸、下行結腸)も増加しています。
40歳以上の中高年に多く、食物繊維の摂取不足の方や便秘で腸管内圧が高まりやすい方にできやすいといわれています。
大腸憩室炎の原因
大腸憩室炎の主な原因は、食物の残渣や便が憩室内にはまり込み、細菌感染を起こすことで発症します。
長引くと穿孔や膿瘍を作る場合もあり注意が必要です。
大腸憩室炎の症状
- 炎症が起きた部分に腹痛が出現します。右側結腸の憩室炎の場合は右下腹部、S状結腸の憩室炎の場合は下腹部が多いです。
- 発熱
- 下痢
症状が現れた場合、早めの診察と適切な治療が必要です。放っておくと穿孔や膿瘍を作ることもあり、激しい腹痛や高熱、血便が出る場合は、緊急を要します。
大腸憩室炎の治療
数日間の絶食、または消化に負担をかけない食事による腸管安静が基本となります。
痛みが生じた時は我慢せず早めに医療機関を受診し、重症化する前に早期治療をすることが大切です。
重症の大腸憩室炎や、穿孔や膿瘍形成などの合併症がある場合は外科的手術を考慮します。
特に、穿孔により便汁が腸の外側に漏れ出て腹膜炎になる方は緊急を要します。
また、憩室炎を年に何回も繰り返される方も手術を考慮する対象となります。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。
この病気は成人の10~20%程度が罹患しているとされており、中高年や高齢者に多い疾患です。
一時的なものは問題ありませんが、長引くと日常生活に支障をきたすためお早目にご相談ください。

逆流性食道炎の原因
食道と胃のつなぎ目には「下部食道括約筋」という筋肉があり、胃の内容物が逆流しないように入り口を閉じる働きがあります。
しかし、この下部食道括約筋の機能が低下すると、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
下部食道括約筋が緩む原因としては、加齢による変化、胃内圧の上昇(食べ過ぎ、早食い)、過食、高脂肪食、過度な飲酒・喫煙、ストレス、腹圧の上昇(肥満、妊娠)、薬の副作用などが挙げられます。
逆流性食道炎の症状
主な自覚症状は胸やけと呑酸です。
特に空腹時や夜間の胸やけを特徴としており、夜中に目が覚めてしまう方もいます。
喉の違和感、咳、声がれ、飲み込みにくさなど食道以外の症状がでることもあります。
逆流性食道炎の検査方法
逆流性食道炎の確定診断には内視鏡検査が有用です。
内視鏡で直接、食道粘膜の状態を観察することができるため炎症の程度にあった治療を行うことができます。
食道裂孔ヘルニア(食道と胃粘膜のつなぎ目の緩さ)も確認することができます。
炎症が激しく悪性と区別がつきにくい状況でも内視鏡の先端から鉗子を出して生検を行い、病理検査を提出する事もできます。
逆流性食道炎の治療
【薬物療法】
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):胃酸の分泌を抑える薬で、逆流性食道炎の主な治療薬として使用されます。
- H2ブロッカー:胃酸の分泌を抑える薬で、短時間で効果が現れる特徴があります。
- 粘膜保護薬:食道粘膜を保護する薬で、炎症の悪化を防ぐのに有効です。
- 消化管運動機能改善薬:消化管の機能を改善する薬剤で、蠕動運動を改善することで胃の内容物の逆流を防ぐ効果があります。
【生活習慣の見直し】
- 食事の内容や量を見直し、高脂肪食や香辛料の強い食事は控える。
- 過度な飲酒や喫煙を避ける。
- 就寝前の食事を控える、食後数時間たってから横になるように心がける。
- 頭を高くして寝るなど、逆流を防ぐ体勢をとる。
- 猫背や前屈みの姿勢を正し、ベルトやコルセットなどの腹圧がかかる服装は避ける。
- 減量する。
胃十二指腸潰瘍
胃十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜および粘膜下層が胃酸などの攻撃により欠落して生じる病気です。
胃酸は本来、食事を分解するために分泌されますが、必要以上に分泌されると自身の胃壁や十二指腸壁を傷つけてしまうことがあります。
また、胃の粘膜を保護する働きが弱まっている人も攻撃によるダメージを受けやすく、潰瘍を発症しやすいとされています。
胃十二指腸潰瘍の原因
- ヘリコバクター・ピロリ菌
胃・十二指腸潰瘍というとストレスや外的要因のイメージが強いですが、そのほとんどはヘリコバクター・ピロリ菌の感染によるものです。ピロリ菌に幼少期に感染すると胃内に生息し続け粘膜が持続的に障害され炎症を起こします。さらに、胃酸や粘膜を保護するための粘液の分泌バランスが崩れ、胃粘膜が傷つきやすくなり潰瘍が生じやすくなります。
- 非ステロイド性抗炎症薬
頭痛や関節痛などの鎮痛、解熱、様々な体の部位の炎症を抑えるために使用されるお薬ですが、「プロスタグランジン」と呼ばれる胃粘膜を保護する物質を抑制する働きがあるため、胃粘膜を守る力が弱まり、潰瘍が生じやすくなります。
- その他
香辛料や塩分などの過剰摂取や暴飲暴食など胃に取り込まれるものが原因となることもあります。また、ストレスなどの精神的負担や胃腸炎などのウィルス感染、遺伝的要因が原因となる場合もあります。
胃十二指腸潰瘍の症状
- 腹痛
胃十二指腸潰瘍の主な症状は腹痛です。
胃潰瘍だと食後、十二指腸潰瘍だと空腹時に上腹部痛や腹部不快感を起こしやすいとされています。
- 胃もたれ
食事の後に胃が重たく感じることがあります。
- 嘔吐
激しい腹痛や胃の不快感が続くと、吐き気や嘔吐を伴うことがあります。
- 吐血
潰瘍が深くなり、血管を傷つけると、吐物に血が混じる吐血をきたすことがあります。
吐血は緊急を要する症状の一つです。
- 黒色便
潰瘍からの出血が消化されると、コールタールのような黒い便がでることがあります。
これも緊急を要する症状の一つです。
胃十二指腸潰瘍の検査
内視鏡検査、胃透視検査、血液検査などがありますが、直接胃の内部を観察できる内視鏡検査が診断に有効です。
- 内視鏡検査
内視鏡を挿入することで潰瘍の位置、大きさ、深さなどの状態を正確に把握することができます。
また、出血をおこす血管が露出していないか確認ができます。もし出血している場合は、その場で止血の処置を行う事もあります。
胃がん等、他の消化器疾患との鑑別診断も行うことができます。
また、胃十二指腸潰瘍はピロリ菌感染が大きな原因となっており、ピロリ菌感染の有無も併せて調べることができます。
胃十二指腸潰瘍の治療
NSAIDsなどの痛み止めを飲んでいる方は中止や変更が必要です。
胃酸分泌を抑える薬や胃粘膜を守る薬などを使用します。
ピロリ菌が陽性の場合は除菌治療を行います。
ピロリ菌
ピロリ菌感染症とはヘリコバクター・ピロリ菌(Helicobacter pylori)によって引き起こされる感染症です。
胃粘膜からは、食物を分解するために胃酸が分泌されていますが、ピロリ菌はこの強い酸性の中でもアルカリ性のアンモニアを作ることで中和し生き残ることができます。このようにピロリ菌が胃の粘膜に住みつくと、長年にわたって炎症を起こし、萎縮性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がん、胃MALTリンパ腫、胃過形成性ポリープなど様々な胃の病気を引き起こします。

ピロリ菌感染症の症状
乳幼児期にピロリ菌に感染した場合、痛覚のない胃粘膜は自覚症状が現れないまま持続感染を起こし胃粘膜に炎症をおこします。
下記の様な症状がピロリ菌の症状と考えられますが、実際は症状のない方も多いです。
- 胃痛
- 心窩部不快感
- 胃もたれ
- 吐き気や嘔吐
- 貧血
ピロリ菌感染症の検査
【内視鏡を用いた検査方法】
- 鏡検法:胃の粘膜を採取し、特殊な染色を行い顕微鏡で観察をする方法
- 迅速ウレアーゼ試験:ピロリ菌がもつウレアーゼという酵素の有無で判定する方法、一般的によく行われる
【血中抗体測定方法】
ピロリ菌が感染すると胃粘膜局所に免疫反応が起き抗体が産生されます。
この血液中の抗体の量を測定することで、感染の有無や感染の程度を判断します。
【尿素呼気試験(UBT)】
ピロリ菌が体内で尿素を分解する性質を利用した検査方法です。
尿素を含む特別な液体を飲んだ後、呼気中の二酸化炭素の量を測定することで、ピロリ菌の感染を確認します。
除菌判定に優れた検査方法です。
【便中抗原測定法】
便を採り、ピロリ菌の一部を直接調べることで感染の有無を確かめます。
尿素呼気試験と同じくらい正確なので、除菌が成功したかを確認するためも用いられます。
ただし、胃酸の分泌を抑制する薬を服用中だと、正確に検査の結果が出ないことがあります。
ピロリ菌の治療
ピロリ菌感染症に対しては、除菌による胃粘膜の炎症所見の改善や萎縮の進行の抑制、胃がんの抑制効果が報告されており、除菌治療が強く推奨されています。
- 除菌治療
標準的な治療は胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)、アモキシシリン、クラリスロマイシンまたはメトロニダゾールの3種類の薬剤を7日間投与する三剤併用療法が用いられます。
クラリスロマイシンは小児科、呼吸器科、耳鼻科などで広く処方されており耐性菌の頻度が上がっていています。それとともに除菌率の低下が指摘されており、適切な薬剤の選択がポイントとなります。
1回目の除菌(1次除菌)終了後2か月以上経った後に、尿素呼気試験または便中抗原検査によってピロリ菌の有無を判定します。ピロリ菌が陰性の場合は除菌成功となりますが、10~20%程度は除菌が成功しないケースがあります。その場合は薬剤を変更して二次除菌を行います。
胃がん
胃がんは、胃の内側にある粘膜の細胞が、何らかの原因によってがん化し増殖を繰り返すことで発生します。
日本は胃がんの発症率が高い国として知られており、発症の要因やメカニズム、早期発見や治療方法についての研究が進んでおり、早期発見し適切な治療を行えば完治を望めるような病気になってきています。
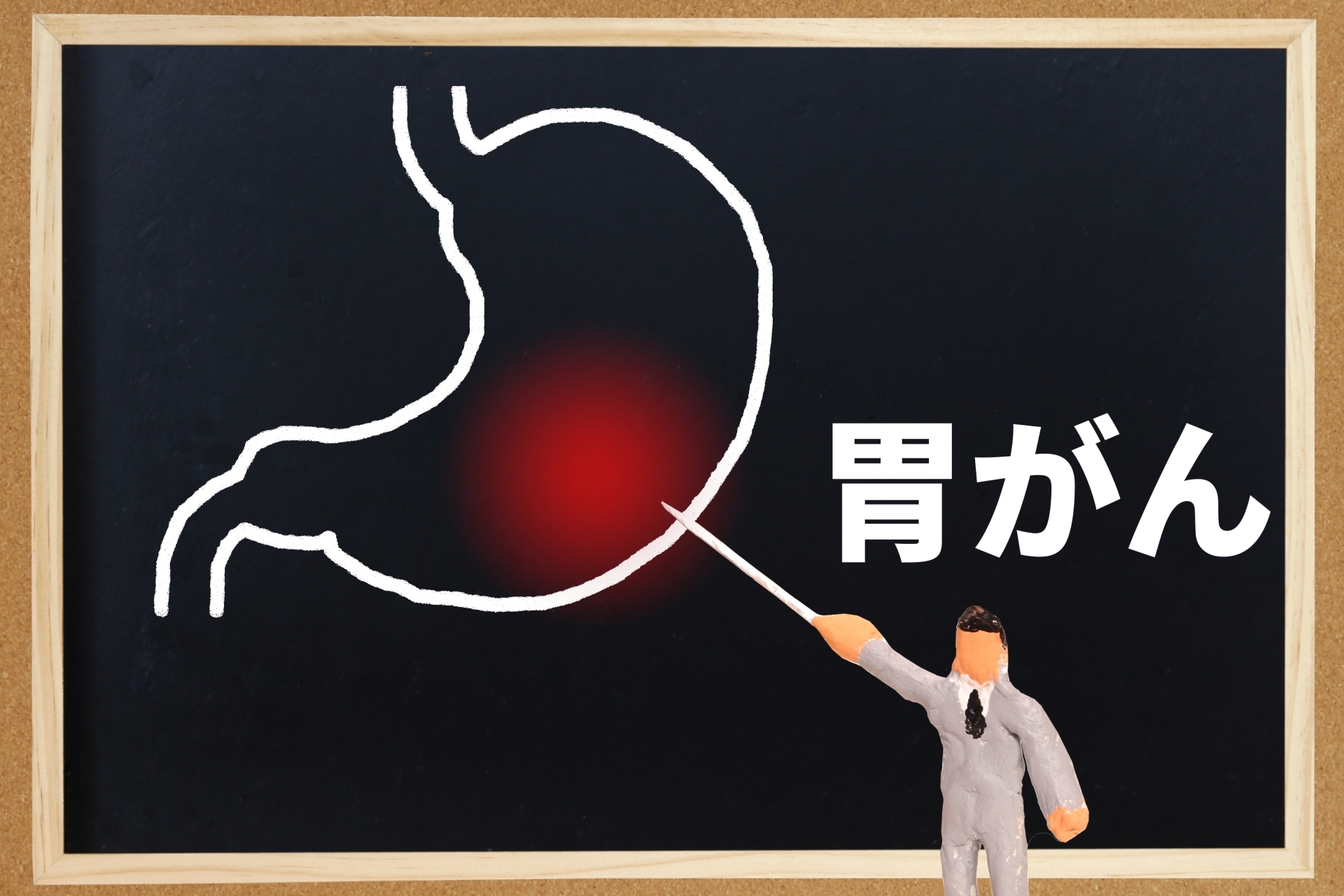
胃がんの原因
胃がんの主な原因としては、塩分の過剰摂取、アルコールの過剰摂取、喫煙、ピロリ菌感染による慢性胃炎などが挙げられます。
ピロリ菌感染がある方が必ず胃がんが発症するわけではありませんが、早めに除菌治療を行うことで胃がんの発症リスクを抑制する効果が期待できます。
胃がんの症状
初期の胃がんは特に症状が出にくく、進行して初めて症状が現れることが多いです。
- 胃痛や胃部不快感
- 食欲不振
- 吐き気
- 吐血や黒色便
- 体重減少
- 喉のつかえ感や飲み込みにくさ
胃がんの診断
胃がんの診断には、いくつかの検査方法がありますが、最も一般的で確実な方法は内視鏡検査です。
特殊な波長の光を使用して胃粘膜を観察し、がんによる粘膜の色調変化を強調する「LCI」観察を活用することにより病変の早期発見に努めております。粘膜を隈なく観察を行い検査中に病変を疑う場合は、内視鏡の先端から鉗子を出し生検することで、病理検査を行い確定診断をつけることもできます。胃カメラ検査は熟練した医師によって行われ、嘔吐反射を抑えたスムーズな挿入を行っています。鎮静剤を使用することでウトウトした状態で検査を終えることも可能です。
胃がんの治療
がんが粘膜層にとどまっていて、悪性度が低い分化型であり、潰瘍やその傷跡がない早期胃がんは大きさに関わらず内視鏡治療の適応となります。悪性度が高い未分化型でも2cm以下で潰瘍やその傷跡がないもの、潰瘍やその傷跡があっても3cm以下で分化型のものは内視鏡治療の適応となります。これらのがんは今までの研究でリンパ節転移の可能性がほぼ無いことが分かっているからです。ⅠA期の約半数はこのように内視鏡治療で治ることが期待できます。内視鏡治療の条件から外れ、遠くのリンパ節や他臓器への転移がないⅠB期、Ⅱ期、III期は手術が選択されます。手術で切除したがんの病理検査の結果で最終的なステージが決まり、術前のステージとは異なることがあります。術後にⅠ期なら経過観察、Ⅱ期とⅢ期なら再発予防目的の術後補助化学療法が行われます。遠隔転移があるIV期は化学療法が選択されます。がん細胞の表面にHER2という分子の受容体がある胃がんでは、トラスツズマブという分子標的薬を用いることで治療効果が高まることが分かっています。
当院の消化器がん予防・経過観察外来では、患者さま個人に合った適切な経過観察を行っています。
機能性ディスペプシア
胃の痛みや胃もたれといった不快な症状が続いているにも関わらず、検査を行っても異常が見つからない状態のことをいいます。
文字通り機能的な問題により症状を引き起こしているといわれています。
消化器内科の診療の中で1番多い疾患で、健康診断を受けた人のうち11~17%、病院にかかった人(病院受診者)のうち44~53%といわれています。命に関わることはありませんが、QOL(生活の質)の悪化をもたらすため、適切な対応が必要です。
機能性ディスペプシアの症状
- みぞおちが痛い
- 胸焼け
- 食事の後に胃もたれがある
- 食欲不振
- すぐにお腹がいっぱいになる
- 胃が重い感じがする
- 吐き気・嘔吐
- げっぷが多い
- 食事が美味しいと感じない
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアの原因はまだはっきりと分かっていませんが、胃の蠕動運動障害、胃の知覚過敏、生活習慣、ストレス、ピロリ菌感染などが考えられています。胃の内容物は蠕動運動により胃から先に送られますが、蠕動運動機能が低下すると、内容物が先に送られずに溜まってしまい、すぐにお腹がいっぱいになったり、胃もたれを引き起こします。知覚過敏では、少ししか食べていないにも関わらず、満腹感を感じます。生活習慣では喫煙や飲酒、脂質過多の食事、不眠が症状と関係していると言われています。また、ストレスが蓄積されると消化管運動機能を調整している自律神経が乱れ、胃痛などを引き起こします。ピロリ菌感染している方に除去治療を行うと機能性ディスペプシアによる症状が改善されることがあります。
機能性ディスペプシアの検査
機能性ディスペプシアの診断としては、胃炎や胃潰瘍、胃がんなど、同じような症状を示す疾患を除外していく必要があります。
まずは胃カメラ検査とピロリ菌感染の有無を調べ、必要に応じて血液検査や超音波検査、腹部CT検査などを行います。
機能性ディスペプシアの治療
【薬物療法】
機能性ディスペプシアの薬物療法として、胃酸の分泌を抑制する薬剤を使用していきます。
また、胃の働きを改善する作用のある六君子湯やアコチアミド、モサプリドクエン酸などを使用することもあります。
ピロリ菌陽性の場合は除菌治療を行います。精神症状が強い場合は、抗うつ薬の服用を検討します。
【生活習慣の改善】
自律神経を整えるためには、規則正しい生活を送ることが大切です。
睡眠不足、不規則な食生活やかたよった食事内容を改善し、暴飲暴食や高カロリー脂肪食を避けることで症状が軽くなることが期待されます。
ストレスも悪化要因なので、ご自身のストレス解消法を見つけておきましょう。
肝臓とは
肝臓は体の中で最も大きな臓器であり、胃の隣に位置します。
肝臓の主な働きは、代謝、分解・解毒、エネルギーの貯蔵、胆汁の合成、免疫機能への関与などが挙げられます。
一方で肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、自覚症状として現れることが少ないため、病気が進行していても放置してしまうことが少なくありません。
肝炎とは、肝臓の炎症であり、その炎症によって肝臓の肝細胞が壊れてしまった状態です。
肝炎の原因としてはウイルス性、アルコール(過食)性、薬剤性、自己免疫性などに分けられます。

脂肪肝
脂肪肝とは肝臓に中性脂肪がたまった状態です。脂肪肝の人の肝臓を超音波検査でみると肝が光っているように見えます、肥満やメタボリックシンドロームに合併しやすく、放置すると肝臓の組織を壊し、肝炎を引き起こします。しかし、脂肪肝は健康診断や人間ドックで肝機能の異常値を指摘されるまで気づかないことも多く、自覚症状がない人がほとんどです。肝機能障害に気づかず、放置してしまうと症状が悪化し、慢性肝炎となり、更に悪化すると肝硬変になります。肝硬変は、肝不全や肝臓がんに進行し、命を脅かす可能性もあります。
- アルコール性脂肪肝
多量飲酒が原因の脂肪肝です。アルコールが肝臓で分解される時、中性脂肪が一緒に合成されるため、肝臓内に脂肪が蓄積します。
- 非アルコール性脂肪肝
飲酒の習慣がない人でも肥満や運動不足などによってインスリンの働きが低下し、血液中の多量の糖分が中性脂肪に変わり、肝臓内に脂肪が蓄積します。
肝炎
ウイルス性肝炎は、その名の通り肝炎ウイルスに感染し引き起こされます。
肝炎ウイルスは、A型、B型、C型、D型、E型などのタイプがあり、それぞれに原因や症状が異なります。
また、A型、E型は慢性化しませんが、B型、C型肝炎は慢性化し、重症化することもあります。
- B型肝炎
B型肝炎は、B型肝炎ウイルスに感染した人の血液に触れる血液感染、体液に触れる性交渉など、B型肝炎ウイルスに感染している母親から出産・授乳を介して感染するケースがあります。急性B型肝炎は、感染してから1~6ヶ月の潜伏期間があり、全身倦怠感、食欲不振、悪心、嘔吐、褐色尿、黄疸などの症状が現れます。症状が激しい劇症肝炎となり死に至ることもあります。慢性B型肝炎は、肝硬変や肝臓がんに移行し命を脅かすこともあります。治療はウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤の内服治療が主に行われます。
- C型肝炎
C型肝炎は、C型肝炎ウイルスが混入した輸血、血液製剤やウイルスが付着した注射器の使い回しなどによって感染します。急性C型肝炎を発症した場合、60~70%の人は体内にウイルスを保持した状態となり慢性C型肝炎に移行し、そのうち10~16%は平均20年ほどの長い時間をかけ肝硬変となると言われます。肝硬変から肝細胞がんに移行するケースも少なくありません。治療は直接型抗ウイルス薬を服用します。
- アルコール性肝炎
アルコール性肝炎は多量飲酒が原因となり引き起こされる肝炎です。多量飲酒をしたすべての人に起きるわけではなく、長期間、常習的に大量の飲酒を続けている人に発症する傾向にあります。アルコール性肝炎の症状は、食欲不振・だるさ・発熱や肝臓がある右上腹部に痛みが出ることもあります。黄疸や紅茶色の尿なども特徴的な症状です。治療は、禁酒と安静ですが、症状が重い場合には入院治療を行うこともあります。
- 非アルコール性脂肪性肝炎
非アルコール性脂肪性肝炎は、過食・運動不足から起きる肥満・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病に合併した脂肪肝から肝炎を発症します。放置すれば肝硬変、肝臓がんへと移行する可能性もあります。治療は、食事療法、運動療法などの生活習慣の改善を行い、生活習慣病の治療も行います。
- 自己免疫性肝炎
自己免疫性肝炎とは、本来、体を守るべき免疫機能が異常をきたし、自分の肝臓の細胞を異物と認識し攻撃してしまうために起きる肝炎です。自己免疫性肝炎については分かっていないことも多く、難病に指定されています。治療は、ステロイド剤などの免疫を抑える薬を使用します。
- 薬剤性肝炎
薬剤性肝炎とは、医薬品やサプリメントが原因となり起こる肝臓の炎症です。 医薬品やサプリメントの成分が原因となる場合と、医薬品やサプリメントが肝臓で代謝されてできた代謝産物が原因となる場合があります。治療は原因薬剤の中止と必要に応じてステロイド剤や抗アレルギー剤などの薬を使用します。
肝硬変
肝硬変とは、慢性化した肝炎が徐々に進行し肝臓が硬くなった状態をいいます。
慢性肝炎によって肝細胞が壊れると、線維化が進んで肝臓が硬くなり、肝臓の機能が著しく低下します。
肝硬変になると肝機能が低下することで、タンパク質の血液中の濃度が低下し、むくみや腹水など様々な症状が生じます。
また、肝臓の解毒作用が低下するとアンモニアなどの有害物質の血中濃度が上昇し、脳機能の低下を引き起こし、肝性脳症と呼ばれる状態になり、意識が朦朧とすることもあります。
肝がん
肝臓がんは、肝臓から発生する「原発性肝臓がん」と他の癌が肝臓に転移し発生する「転移性肝臓がん」の2つのタイプがあります。
肝臓がんは転移性がんから発生するケースが多く、原発性肝臓がんの4-10倍と言われます。
日本での肝臓がんの原因は、B型やC型肝炎ウイルスの感染による慢性肝疾患からの移行が原因の約80%を占めていました。
しかし、近年では抗ウイルス薬によりウイルス性肝炎が克服され、ウイルス性肝炎が原因で生じる肝がんは減少しています。
一方で肥満の増加により、非アルコール性脂肪性肝炎などの生活習慣に関連する肝がんの発生が増加しています。